ガルプSWダブルウェーブ3” は本来、ロックフィッシュ用ルアーとして開発したものだが、その優れたポテンシャルから様々なジャンルの釣りでも応用が効く。
今回はそんなダブルウェーブをバスフィッシングに用いる際に効果的な活用方法についてお伝えします。
湖・沼・河川・野池など多種多様なフィールドが舞台となるバスフィッシングにおいて、特に小規模な沼や野池など人的プレッシャーの高いエリアではスピニングタックルを駆使したライトリグ・フィネスリグの釣りが主体となることも多い。そのような状況下でも効果を期待出来るリグの一つとしてノーシンカーリグの存在が挙げられる。ダブルウェーブはその見た目よりも自重があることから、タックルを吟味すればノーシンカーでも想像以上の飛距離をかせぐことも可能で、更に繁茂するウィードの上や表層をグラビンズバズで引けば、独特の水ヨレを発生させながらバスを四方から効率良く引き付ける。要は小さなバズベイトだ。グラビングバズで通す際は前方のカーリーレッグや後方のカーリーテールをそのまま残した状態(※前方のカーリーレッグだけ左右カットして使用するのも効果的)で使うものの、私が特にオススメしたいのはイモグラブとして使用する方法だ。
又、テールがちぎれてしまったダブルウェーブを再利用する方法としても、この使い方は一石二鳥。
 推奨オフセットフックは根魚アングラーには毎度お馴染みながら、そのフッキング性能の高さから意外にもコアなバスアングラー達からも高い評価を得ている岩礁カウンターロック の1/0がベスト。これを後方重心になるようにオフセットフックにリグると飛距離の増大に繋がるだけでなく、ラインスラッグやラインテンションの張り方次第では、ややバッグスライド気味にフォールさせアプローチするこも可能。
推奨オフセットフックは根魚アングラーには毎度お馴染みながら、そのフッキング性能の高さから意外にもコアなバスアングラー達からも高い評価を得ている岩礁カウンターロック の1/0がベスト。これを後方重心になるようにオフセットフックにリグると飛距離の増大に繋がるだけでなく、ラインスラッグやラインテンションの張り方次第では、ややバッグスライド気味にフォールさせアプローチするこも可能。
 私の場合は画像2枚目のようにヘッド部分の水抵抗を軽減し、よりウィードレス効果も望めることから後方重心になるようセットするケースが多いものの、逆付けセッティングのみならず、3枚目の画像下段のように通常セッティングするようにリグっても勿論、使用出来る。
私の場合は画像2枚目のようにヘッド部分の水抵抗を軽減し、よりウィードレス効果も望めることから後方重心になるようセットするケースが多いものの、逆付けセッティングのみならず、3枚目の画像下段のように通常セッティングするようにリグっても勿論、使用出来る。
 オーバーハング最奥のシェードへスキッピングで投げ込んでフォール中にバイトを捉えるのもよし、軽くトゥイッチしつつ細かくドッグウォークさせてイレギュラーアクションを与えるのも◎
オーバーハング最奥のシェードへスキッピングで投げ込んでフォール中にバイトを捉えるのもよし、軽くトゥイッチしつつ細かくドッグウォークさせてイレギュラーアクションを与えるのも◎
浅めに設定したハイピッチラウンドリブボディーから発する微波動とクイックリーなその動きでシャローにステージングするバスにも有効なダブルウェーブのイモグラブセッティンング。海だけでなく、バス釣りもされる皆さんはぜひ一度試してみて下さい。
野池など小規模フィールドや「ここぞ!」というピンスポットではめっぽう強い使用方法です。
2011年6月7日 |
カテゴリー:製品情報
昨年度で前メーカーの契約任期満了に伴い、今年度(2011年4月期)より新たなライン部門スポンサーとして私儀、株式会社クレハと契約締結したことをご報告させて頂きます。あのテレビCMでお馴染み「NEWクレラップ」の会社としては勿論のこと、釣り業界においてはフロロカーボンラインのパイオニアメーカーとして知られ、ジャンルを問わず多くの釣り人から愛用されているのはご周知の通り。各社の仕掛けのハリスや幹糸の多くに採用されている「シーガー 」シリーズをはじめ国内で唯一、原料から製造まで一貫して自社内でフロロカーボン開発生産体制が整っている大手化学メーカーでもあります。
特性上、常に“根ズレ”の脅威にさらされるロックフィッシュの釣りに求められる高品質ラインにおいて、世界でもわずか数社しかないフロロ原料メーカーであるクレハ独自の高度な研究開発技術と幾多のフィールドワークで培ってきた私のノウハウを共有していくことで、この痛快極まりないロックフィッシュシーンを更に発展させて参りたいとの思いから、この度ライン部門契約メーカーとして合意に至りました。
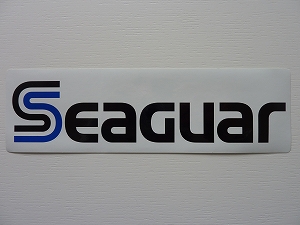
フロロカーボンのパイオニアと根魚釣り師の共演。
ロックフィッシュシーンは、北国の釣りは、また一歩新たなステージへと踏み出していきます。
2011年6月6日 |
カテゴリー:その他
本来であれば震災の前日、3月10日に掲載予定でした「ダブルウェーブの使い方3(ジグヘッドリグのセッティング方法)」をまだ公表していなかったので、発売のタイミングに合わせまして改めて本日掲載致します。 尚、ユーザーの皆様方がこのワームの優れたポテンシャルを最大限に引き出し効果的にご活用頂けることを願い、引き続き開発者ならではの視点からダブルウェーブの使い方についての【応用編】も順次掲載していきます。
※バックナンバーはこちら↓
オフセットフックの刺し方1
オフセットフックの刺し方2
■ ダブルウェーブの使い方3(ジグヘッドのセッティング方法)
ガルプSWダブルウェーブ3” は多彩なリグに広く活用出来る点も魅力です。その中でもテキサスと並び私の一押しリグが、ジグヘッドとダウンショット。とりわけ太平洋側・日本海側問わず東北地方では古くから根強い人気を誇るクロソイのナイトゲームと北海道におけるアイナメ・クロソイ狙いでの堤防&沖堤の際狙いのフォーリング~スイミングでの横トレース釣法(オカッパリ・ボート問わず)にも最適なのです。
今回はそんなダブルウェーブをジグヘッドで使いこなす際のワンポイントアドバイスを。とても簡単なので、ぜひ覚えて頂けたら幸いです。
まず、ダブルウェーブをジグヘッドにセットする際、ヘッドウェイトが3/16ozまでであれば、そのままご使用下さい。逆に1/4oz以上のジグヘッドを使う際には、1枚目の画像のように頭部の第一関節(くぼみ部分)をカットしてジグヘッドをセットするとジグヘッドとワームの一体感が増し、ワームの“座り”がより一層安定するようになります。
部分までカットして下さい。.jpg) 北海道ではアイナメ・クロソイをジグヘッドで狙う場合、オカッパリでは1/8oz~3/16ozを中心に1/4ozまでの出番が大半ですよね。ボートロックの際でも3/16oz・1/4ozを基準に重くても3/8oz~1/2ozまでが通常。
北海道ではアイナメ・クロソイをジグヘッドで狙う場合、オカッパリでは1/8oz~3/16ozを中心に1/4ozまでの出番が大半ですよね。ボートロックの際でも3/16oz・1/4ozを基準に重くても3/8oz~1/2ozまでが通常。
一方、磯場や底根のボトムが多い東北太平洋側では、それが例え沖堤であったとしても防波堤の際にはダイレクトに魚が寄っていないことが多く(仮にいても小型魚の場合が多いため)、それなりの良型・大型を狙って釣ろうとなれば防波堤の際ではなく、沖の深場に向かってロングキャストし周囲の根周りを広く探る必要があるため(※ここが北海道と東北の環境が大きく異なるところです)、防波堤オカッパリでもメインは1/4oz~と北海道よりも平均的に重いウェイトのジグヘッドを多用する傾向にあります。
ダブルウェーブは普段、私が使用しているOHラウンドヘッド(JH-11)やラウンド15システム(JH-15)は勿論、現在、市場に流通している様々なジグヘッドとのセッティングを考慮し、ジグヘッドのワームキーパー部分の太さとワームのヘッドの太さが極力合うように設計しました。よって、ワームキーパーの部分が太くなりがちな1/4oz以上のジグヘッドの場合は予めワームの第一関節のくぼみまでカットしてセットするとキレイに収まります。
又、このワームの特性上、ジグヘッドリグでの使用では1/8oz~1/2ozまで対応するうち、3/16oz~1/4ozにかけてが最もキレイに【なびきアクション】することも知っておいてほしいです。
あくまで軽やかで、ゆったりとしたフォールを織り交ぜてアプローチをするのがコツ。1/2oz以上のヘビーウェイトジグヘッドではフォールスピードが速すぎてワームの動きがタイト気味なってしまうので、ダブルウェーブ本来の動きは若干出しにくくなる(※マダイの一つテンヤ使用時は除く)ということを頭に入れておいて頂ければ完璧です。
2011年6月3日 |
カテゴリー:製品情報
早いもので今日から6月。
私は7月の生まれということもあってか、一年のうちで最も好きな季節が夏です。中でも冬の寒さから解放され、多くの生命がいっせいに躍動する新緑の季節が一番好きです。
今しか味わえない瑞々しい葉の美しさに光の力、これから本格的な夏に向かっていく楽しみ、期待感が大きく膨らみます。
釣りに関してもそう。6月はバスにトラウト、ロックにフラット、シーバス、クロダイ…と多くの魚達が好期を迎える。北海道の巨大クロソイは乗っ込み真っ最中だし、バスはスポーニングから解放されアグレッシブにエサを追い求め、山々に足を向ければ美しき渓魚達が出迎えてくれる。 おっと、サクラマスの存在も忘れてはいけない。例年、実はまだ多くの個体が下流域に残留している北上川水系のサクラマス。秋田県の川も今日が解禁だ。北海道の日本海側では、まだ銀ピカの海サクラが残っているはずだし、これから盛夏にかけて道東サーフでは丸々太った海アメが回遊する。道北のニジマスも期待大だ。
 あれこれ想像しただけでも、なんかこう…ワクワクしてきませんか!?
あれこれ想像しただけでも、なんかこう…ワクワクしてきませんか!?
例年、私の釣行回数が一番多かったのも6月。いつもこの時期、地元を離れてあちこち遠くまで釣り歩くから、ロックロッドにトラウトロッド、バスロッドもシーバスロッドも…と、持参するロッド本数も尋常ではないわけです。
今年は少し“おとなしく”していようと思っていますが、気持ちは既にあの海へ、あの川へ飛んで行っている次第。
私とて、皆さんと同じ釣り人なのです。
さぁ、そろそろ貴方も出かけてみませんか。
海も川も湖も。生命溢れる、緑のパワーを解き放て!
2011年6月1日 |
カテゴリー:その他
ダブルウェーブの開発には長い研究期間と試行錯誤を要したことは、釣りビジョンモバイルサイト「佐藤文紀コラム」読者の皆さんならご存知の通り。
従来のガルプワームでは対応出来ない状況、つまり苦戦を強いられるタフコンディション下においても、何とか魚を引っ張り出してくれるお助けワームとして、その全てが根魚専用設計に基づいている。それはカラーもしかり。
ワームのカラーは塗料素材によっても硬さや粘り気が大きく左右される。ある程度、経験を積んだアングラーであれば、「同じワームなのに色が違うとこんなにも素材感が違うのか…」と感じたことがあるはずだ。特にガルプという素材は優れた生分解性と強烈なニオイの煙幕を周囲に放出することから、今や“釣れるワームの代名詞”にまで認知されるようになったが、その元を辿ると天然成分ゆえに素材コントロールが非常に難しい素材でもあるのだ。
そのため、パワーベイト素材では実現可能なアクションや機能もガルプ素材では成形不可というデザインやアイディアも少なくない。ダブルウェーブに至っては最初からガルプ素材で作ることを念頭に置き、開発を進めてきた。
一般的にパール顔料を配合して成型するとワームは硬く、張りが強くなる。クリアカラーのワームに比べ、パールホワイトに代表されるパール顔料配合系カラーのワームの方が硬く感じるのはそのためだ。極端な例ではあるが、貝殻を粉々に砕いて塗料に混ぜ込んだ物がパール顔料だと思っていただければイメージしやすいかもしれない。これらは粒子が大きい(粗い)ため、成型加工した際にどうしても素材本体に張り(パツパツ感)が出てしまい結果的にこれがワームの硬さを助長する要因の一つにもなる。一方、クリアカラーはクリアカラーなりの難しさもあって、顔料面で硬さの調整が微妙なため、素材本体に張りが無さ過ぎる“ゆるい状態”(ベロベロ感)で成型されてしまうケースもある。
ロックフィッシュの定番カラーである赤色、その中でもマットレッドあるいはソリッドレッドと共に人気の赤系カラーとしてクリアレッドの存在があるが、バークレイの既存カラーラインナップで例えるとレッドバグキャンディーがこれに近い。
 レッドバグキャンディーカラーをガルプ素材で成形すると、独特のモチモチ感がある柔らかさが出るのだが、この良し悪しはその人の捉え方に大きく委ねられる。ワームが柔らかい分、喰いのシブい時でも喰い込みが良いからいい(フッキング率の向上)、という人もいれば、ハードに使うとすぐにワームがズレて使い勝手がちょっと…と思う人もいるはずだ。
レッドバグキャンディーカラーをガルプ素材で成形すると、独特のモチモチ感がある柔らかさが出るのだが、この良し悪しはその人の捉え方に大きく委ねられる。ワームが柔らかい分、喰いのシブい時でも喰い込みが良いからいい(フッキング率の向上)、という人もいれば、ハードに使うとすぐにワームがズレて使い勝手がちょっと…と思う人もいるはずだ。
ダブルウェーブは根魚専用設計ワームとして、この点まで徹底したこだわりを貫いており、レッドバグキャンディーの硬さ調整には最後の最後まで時間を費やした。せっかくキレイな動きを発生するワーム本体のアクションには影響の出ない範囲で、ジグヘッドリグでの串刺しでも、テキサスやダウンショットなどオフセットフック使用時でも適切なフィーリングを得られるよう素材感の微調整とテストを繰り返しおこなった。
満を持して登場する、タフコンディションの切り札「ガルプSWダブルウェーブ3”」。
生みの親として世に送り出す喜ばしさと共に、同志である全国各地の皆さん方のお役に立つことを願ってやみません。
2011年5月31日 |
カテゴリー:製品情報
« 前のページ
次のページ »
 推奨オフセットフックは根魚アングラーには毎度お馴染みながら、そのフッキング性能の高さから意外にもコアなバスアングラー達からも高い評価を得ている岩礁カウンターロック の1/0がベスト。これを後方重心になるようにオフセットフックにリグると飛距離の増大に繋がるだけでなく、ラインスラッグやラインテンションの張り方次第では、ややバッグスライド気味にフォールさせアプローチするこも可能。
推奨オフセットフックは根魚アングラーには毎度お馴染みながら、そのフッキング性能の高さから意外にもコアなバスアングラー達からも高い評価を得ている岩礁カウンターロック の1/0がベスト。これを後方重心になるようにオフセットフックにリグると飛距離の増大に繋がるだけでなく、ラインスラッグやラインテンションの張り方次第では、ややバッグスライド気味にフォールさせアプローチするこも可能。 私の場合は画像2枚目のようにヘッド部分の水抵抗を軽減し、よりウィードレス効果も望めることから後方重心になるようセットするケースが多いものの、逆付けセッティングのみならず、3枚目の画像下段のように通常セッティングするようにリグっても勿論、使用出来る。
私の場合は画像2枚目のようにヘッド部分の水抵抗を軽減し、よりウィードレス効果も望めることから後方重心になるようセットするケースが多いものの、逆付けセッティングのみならず、3枚目の画像下段のように通常セッティングするようにリグっても勿論、使用出来る。 オーバーハング最奥のシェードへスキッピングで投げ込んでフォール中にバイトを捉えるのもよし、軽くトゥイッチしつつ細かくドッグウォークさせてイレギュラーアクションを与えるのも◎
オーバーハング最奥のシェードへスキッピングで投げ込んでフォール中にバイトを捉えるのもよし、軽くトゥイッチしつつ細かくドッグウォークさせてイレギュラーアクションを与えるのも◎






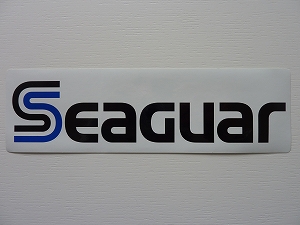
部分までカットして下さい。.jpg)


 レッドバグキャンディーカラーをガルプ素材で成形すると、独特のモチモチ感がある柔らかさが出るのだが、この良し悪しはその人の捉え方に大きく委ねられる。ワームが柔らかい分、喰いのシブい時でも喰い込みが良いからいい(フッキング率の向上)、という人もいれば、ハードに使うとすぐにワームがズレて使い勝手がちょっと…と思う人もいるはずだ。
レッドバグキャンディーカラーをガルプ素材で成形すると、独特のモチモチ感がある柔らかさが出るのだが、この良し悪しはその人の捉え方に大きく委ねられる。ワームが柔らかい分、喰いのシブい時でも喰い込みが良いからいい(フッキング率の向上)、という人もいれば、ハードに使うとすぐにワームがズレて使い勝手がちょっと…と思う人もいるはずだ。